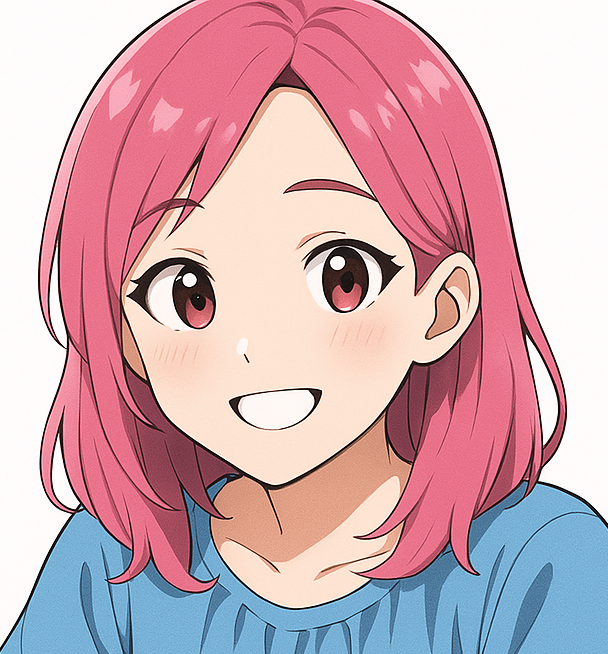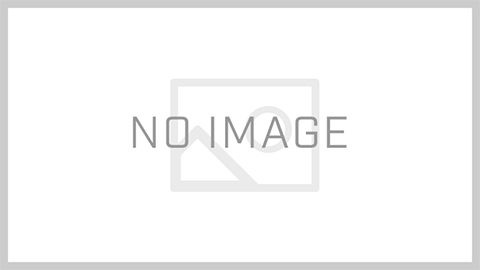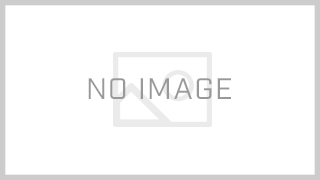こんにちは、エミリーです
私たちは、共働き・子ども2人・賃貸住まいのごく普通の4人家族
決して高収入ではありませんが、「40歳までに3,000万円貯める」という目標を掲げ、5年間コツコツと節約・投資に取り組んできました
結果、節約・投資から約5年で資産3,000万円に達することができました
このブログでは、実際に達成した3,000万円を貯蓄する思考法をご紹介します
未就学児にお金の教育?(早いんじゃない)
早くからお金の教育をする事のデメリットはあります
ですが、それ以上にメリットがあると感じているため 私たちは子どもに「お金の教育」をすると決めました
大きなデメリットとして考えられるのは以下2点
- お金の重要性を強調しすぎて、子どもが物事の価値を金銭的な基準でのみ判断するようになる可能性
- 家庭の経済状況が子どもに伝わることで、劣等感や不安感を感じさせる可能性
一方、メリットとして考えられることは沢山あります
- 家計管理能力が向上する
- 働くことの価値を理解できる
- 将来設計能力の向上
- 税金や社会保障の理解
変化の激しい社会において、その国のルールを理解することと
自分が一時の快楽に流されず、適切に自分を律すること(例えば、将来働けなくなる可能性もあるから、収入の一部は貯蓄に回そうとか)が、自分の身を助けることだと考えています
なので、子どもの負担にならない範囲で、朝の登園時間やスーパーに行ったときなど都度都度のタイミングでお金について話題に出すようにしています
また、上の子が5歳になったこともあり
週末の予算(5,000円)で家族全員で何をしたら楽しめるか?について
考えてもらうのもおすすめ(詳しくは後ほど)
具体的に、どんなことをしているの?
大前提として、
<子どもの負担にならない><子どもが過度な不安を抱かない>ということ
つまりは<子どもの安全は担保されている>という話を毎度のようにしています
「幸せになる」ために教えてるから「不安」を先に解消してるよ!
前提として話してるのは、こんなこと
- 私が働いてるから、暮らす家・ご飯の心配はしなくて大丈夫だよ!
- 君たちが保育園に行ってる時に、働いてるんだよ
- 保育園に行ってくれてありがとうね
- もし、辛いことがあったらいつでも言うんだよ
- 君たちを幸せにするために、私は頑張れるんだよ
こういった趣旨のメッセージをちょっとずつ子どもに投げかけてます
もちろん、聖人君子ではないので
子どものちょっとした言動にイライラしたりすることもあるけど
その時は 「あの時は母ちゃんが悪かった」と謝るようにしています
お金で子どもに話すこと
「お金の教育」といっても、未就学児では
複利計算や借金とはどういうものかなど、高度なことを理解することは難しいです
なので、生活に根ざしたものを話題にしてお金のことを話しています
例えば、保育園で使っている「カトラリーセット」
新品が欲しい →値段は1,300円だった
中古 →傷がついているけど300円
この差1,000円で何ができると思う?と考えさせる
そして、祖父母からもらった新品(同じ系統が望ましい)を思い出す
1ヶ月も立つと傷がついてボロボロになってる
何も魅力がなくなっている
1,000円も高い新品にその価値はあるのか?を考えさせる
数字の感覚がない子どもには、モノに換算して教えてあげる
例えば1,000円あるとドーナツ(子どもの大好きな嗜好品が望ましい)が5個買える
新品を買って、ドーナツ5個食べられないのと
中古を買って、ドーナツ5個食べるのと、どっちがいい?
と尋ねてみる
本人に<考えさせる>ことがポイント
価値観を数値化する
価値観を数値化できれば、自分が何にお金を使えば幸せになれるのかわかる
特に、自分で使えるリソース(お金)が少ない場合には
何にどれだけ分配するか?が非常に制限されるので、より難しくなる
これは、大人の<自分では気づかない無駄遣い>をなくすのにも有効
無理せず、生活に根ざしたものを
特に難しいことをしているわけではなくて、
お金は自分の望みを叶えられる引換券なのだということと
自分が幸せになれることにお金を使うべきで、それ以外のものにはお金を使わない。
ということが大事なのだということを伝えている
その話のタネは、道中あちこちに転がっている
「水筒の水を持っていくのか、自販機で飲み物を買うのか?(自販機で購入すると、誰かが持ってきてくれた美味しい飲み物を買えるが、その価値は?)」
「靴が小さくなってきたとき、痛いけど我慢して履き続けるのか?それとも嗜好品をやめて新しい靴を買うのか?(健康と嗜好品のどちらがより大切か?)」
などなど・・・
子どものお金の教育を通して、親が学ぶ
この話を子どもにすることで、自分自身が学ばせてもらっていると感じる
お金をかけるべきところは何なのか?
最小限の資源で、最大の幸福を得られるものは何か?
その方法は他にはないのか?
もちろん、機械ではないので間違うこともある。
子どもも間違うし、親も間違うという姿を見せられる
だけど、その度にリカバー出来る範囲(致命傷を負わない範囲)で、いろいろと試してみることの大切さを感じられる。
そして、最大の幸福とは何なのか?「今この瞬間」の幸福ではなくて、面で見てみる。(時間軸)体積で見てみる。(このモノは自分だけでなく家族を幸せにするか?)
これを徹底的に考えさせられる